「スポーツ共創」とは何か。 インタビュー:江渡浩一郎(産業技術総合研究所 主任研究員)
柿崎俊道(編集者)
江渡浩一郎氏(産業技術総合研究所 主任研究員)は「スポーツ共創」という言葉を運楽家 犬飼博士とともに生み出し、共創社会を提唱している。江渡氏に「スポーツ共創」の根幹とその発展について聞いた。

東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了。博士(情報理工学)。
産総研では「利用者参画によるサービスの構築・運用」をテーマに研究を続ける。
2017年、科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(理解増進部門)受賞。
「ユーザー参加」から「共創」へ
―― 江渡先生は「スポーツ共創」を提唱し、共創型イノベーションという言葉もお使いになられています。イノベーションが起きる場は「ユーザー参加」から「共創」へと移り変わる、と。ユーザー参加と共創とは違うということでしょうか。僕は同じものだと思っていました。
江渡浩一郎 ひと言でいうと、違います。「共創」という言葉は大変幅広く使われています。ユーザー参加の意味で使う人もいるとは思います。しかし、ユーザー参加と共創の大きな違いは、共創の方がより深く対象にコミットする、という点です。「ユーザー参加」は企業や主催者から参加者に土台が与えられて、土台に自作の動画を投稿してもいいよとか、その土台の上で何かをつくってもいいよというのが、一般的な解釈だと考えています。
―― 土台とは、言葉を変えるとプラットフォームですね。動画配信サービスのような。
江渡 そうです、わかりやすいのはYouTube(ユーチューブ)ですね。僕の考える共創はそうした対象に一段深くコミットするようなものと思っている。参加者が土台の姿そのものからコミットして変えていく。参加している人が土台を育てていくイメージが僕の考える共創です。
―― 土台、プラットフォームの部分からコミットする……。スポーツ共創の「未来の運動会」の場では、運楽家の犬飼博士氏が参加者をデベロップレイヤー、ファシリテーターやディレクター、プロデューサーと割り振ってイベントを構築しようとしています。なるほど、皆でいっしょに運動会のプラットフォームからつくるんだよ、という意志がそこにはある、ということですね。それは、江渡先生の仰る土台の部分からつくっていく「共創」のように感じます。
江渡 一方で「ユーザー参加」は会社という組織が用意した土台の方針に沿えば、ユーザーは「動画を投稿することが出来ますよ」「コメントすることができますよ」「動画のリストをつくることができますよ」となる。YouTubeの形ですね。
「共創」の形にあるのが、Wikipedia(ウィキペディア)です。これはWikiという仕組みを使い、ユーザーが自由に中身を書き換えられる。YouTubeとWikiを比べると「ユーザー参加」という意味では同じだけれど、Wikiの方がユーザー参加の度合いが強いと感じる。それは何が違うのか。
Wikiは、ジミー・ウェールズとラリー・サンガーのふたりが中心になってネット上に「百科事典」をつくることを目的につくりはじめました。最初期の段階から、Wikiは編集の仕組みそのものを含めてユーザー参加でつくり上げていく、という方針を少数のチームで立てた。その過程は今も全て残っていて、Wikipediaのコアとなる部分を形作っています。
ユーザーとともに「百科事典をつくる」という目標は決まっている。しかし、百科事典をどのようにつくるのか、といったところも含めてユーザーと共につくり上げるのが、Wikipediaの姿勢なんです。それは特異であり、画期的だった。その姿勢がWikipediaをインターネット上で特殊なサービスにした理由だと考えています。
―― 未来の運動会の場もそうですが、共創の場には多様な方がいらっしゃいます。バックボーンはさまざま、スキルの種類やレベルもバラバラ。その中で「土台部分から、どうぞつくりましょう」「一緒につくりましょう」となると、非常にアグレッシブな展開がはじまりますよね。物作りに突き進んだり、突き進まなかったり、ときにはふさぎ込んだりします。でも、それも含めて新しい価値はそこから広がっていく、ということですか。
江渡 そういう認識です。その通りです。
市民が土台(プラットフォーム)から変えた「特定非営利活動促進法」
―― 今の日本社会を考えると、ある程度の試験を通って入社してきた人たちが、グループとして固まって物事をつくった方がスムーズなんじゃないか、と。どうしても僕はそちらに意識が巡ってしまいます。
江渡 その形で社会全体が発展してきました。かつ、日本はだいぶ完成された社会なわけです。近代社会においてはある程度、固定化された仕組みがあり、それに基づいて国家が運営されてきた。その中には学校、会社という仕組みがある。でも、社会そのものが大きく変わることがある。それは仕組みの形がない状態で現れて、その後、しばらくして形が定着する、という道を辿ります。
具体的な話をします。1995年の阪神淡路大震災の時のことです。ボランティアが集まって、救助活動をはじめとした様々な活動を行いました。それがボランティアベースで様々な大規模な救援活動が行われた国内で最初のケースだといわれています。はじめてのケースですから、活動中にいろいろな弊害が出てきます。世界中から義援金が集まりました。しかし、それを受けるはずのボランティア団体は任意の市民団体です。法人格を持たないため、会計監査に則った経済支援を受けられません。その弊害は思ったよりも大きく、この問題は社会全体で大きく認識されました。そこで、3年後の1998年に「特定非営利活動促進法」が制定されました。特定の目的だけに用いられる非営利な団体という仕組みが市民の要望から生まれたのです。特定の条件を満たせば「特定非営利活動法人」という法人格を得られるようになりました。それが「NPO」という仕組みが生まれた歴史的経緯です。
「特定非営利活動促進法」こそ、土台を書き換えた事例といえます。ボランティアは目の前の人を救おうと集まりました。人を救うためには組織をつくらなければいけないから、ボランティア組織をつくった。それは単なる任意団体ですから、人を救うための力を備えることができなかった。力を得るためには土台そのものを書き換えるしかない、と気付いた。そして、市民は政治に働きかけ、政治家は立案し、特定非営利団体という仕組みをつくり、社会は目の前の人を救うための力を得たわけです。これこそが、社会を進展させる力です。そして、そうした動きが、さまざまなところで発生しています。
―― 今、お話を伺っていると恐ろしいことだと感じました。恐ろしいというのは、個々人がどんどんぶつかるわけですから。共創という、共につくるためにはお互いに痛みあいながらつくっていくということですよね。江渡先生が例に出されたボランティアの皆さんは文化も年齢も性別も、国籍も違う人たちが集まってきたことでしょう。どうNPOをつくるのか、というぶつかり合いが発生する。そうした共創を考えるときに、片方で「独創」という言葉が浮かびます。なぜ、独創ではなく、共創なのでしょうか。
江渡 独創と共創は、僕は相反する概念ではないと思っています。簡単にいうと共創の前提条件が独創なんですよ。独創をする能力がない人が集まっても、共創は生まれません。何よりもまず大事なのは独創です。独創する人が集まって、ぶつかり合った時に、共創が生まれます。
クリエイティビティは人類史にあり

―― なぜ今、共創と仰るのでしょうか。広く考えれば、従来も共創だったのではありませんか? 入社試験を通って、面接を受けて、特定の会社に入る資格を得て、社内でチームを組み、プロジェクトを実施する。それも共創ではありませんか。
江渡 ざっくりいうと、その通りです。昔のスタイルの共創は、特定の1種類の型があり、その型にはまった人を募集し、それをさらに型にはめて、ひとつのことをうまくできるようにする、という仕組みです。うまくできる人が集まって会社という組織をつくり、1種類の製品をつくる。1種類というのはクルマ会社だったら自動車をつくる、という意味です。同じ商品を大量に生産して世界に広めて利益を得ると企業活動になります。
それが悪いわけではありません。ただ古くなってしまった。つまり、今の社会に合わなくなった。一方で新しい仕組みをつくる経験をこれまでしてこなかった。過去にたまたま出来上がったに過ぎない「画一的な人を前提とした会社」という仕組みが動かしにくくなっている。社会では「共創」が問われているのではなく、「創造性」が問われているんです。クリエイティビティがね。
―― クリエイティビティが問われている?
江渡 会社としてのクリエイティビティが問われている。新しい製品をつくらなければいけないのに、それが出来なくなっている。クルマ会社だったら自動車をつくるのが仕事だと思っていた。けれども、どうやら世界は変化しているぞ、と気付いた。クルマ会社は「自動車を前提として考えたらダメだ」「人が移動するということから考えなければいけない」みたいなことにようやくたどり着いた段階なんです。しかし、「人が移動することから考えよう」というのは、クルマ会社以外の他の会社はすでに口にしていることでもある。当のクルマ会社が慌てて、追いつくためにはどうしたらいいのかを頭を使いはじめたのです。
先を行っている人や企業はどうしてそれがわかるのでしょうか。クリエイティビティがあるからなんですよ。発想力があり、オリジナリティが備わっている。それでは、その発想力やオリジナリティはどこから身に付くのか。それは、過去の歴史からです。
―― 歴史のなかに発想力があり、オリジナリティがある?
江渡 過去の資産といってもいい。それはいろいろな意味の資産です。いわゆる人類史であり、その中に芸術だったり、文学であったりとか、技術がある。人類史を広く知れば、今まで変化してきた社会がこれからどうなるのかを予測できる。それを傍から見ると、イノベーションを起こした人、つまり、イノベーターに見える。だけど、実際にやっていることは単に歴史の先を読んでいるだけです。
そのなかで「共創」がなぜ問われているのか。そこはややわからないところがある。独創的な能力がある人がイノベーションを起こし、ブームとなり、席巻しますよね。その変化は、ITの発展のおかげで、世界中に瞬時に届くようになりました。
―― ひとりの偉業はすぐに世界に広がりますね。どこそこの地域や企業の「この人がすごい」という情報はあっという間にネット上に行き渡ります。
江渡 そのスピード感が世界的な大変化です。すると面白いことに、独創性の価値が減ずるわけですよ。つまり、独創的な人によって考えられた独創的なアイデアが瞬時に世界に広まる、という世界が生まれました。
独創性疲れを打破するための「共創」

―― イノベーションが世界に広まることによって、あっという間に独創性が消費されてしまう?
江渡 おそらく世界が思っても見なかった変化のひとつでしょう。従来型の変化から考えると、「世界へ広まる」という段階はワンステップ先なんです。画一的な大量生産の時代からすると、思ってもみなかった新商品を考える人は「偉い」わけですよ。その人たちはイノベーターと呼ばれて、イノベーションを起こしてきた。
ITによってもたらされた状況の変化は、世の中をイノベーターだらけにしたことです。世界の変化は加速した。加速しすぎるとどうなるかというと、当然揺り戻しが生まれてくる。世の中が「独創性疲れ」になってきた。
「独創性疲れ」をわかりやすく整理します。新商品が出てきて真っ先に飛びつく人をアーリーアダプターといいます。そのアーリーアダプターが伝えた情報をもとに商品をいち早く使おうとする人たちがいます。この人たちはアーリーマジョリティと呼ばれています。アーリーアダプターとアーリーマジョリティとの間に、キャズムという溝があります。
―― アーリーアダプターが使用した商品やサービスがアーリーマジョリティに届くと、大ヒットを生み出す。「キャズム越え」といわれていますね。
江渡 今、そのキャズムを巡って変化がはじまりました。要するに新しいモノが好きなアーリーアダプターは以前と変わらず商品を使いまくっているけれど、ふと振り返るとアーリーマジョリティが誰もついてこない。キャズムを越えないケースが増えてきたのです。
思い出してください。流行るかな、と思ったけれど廃れてしまった商品はたくさんありますよね。たとえば3Dテレビです。3Dテレビは業界全体で大々的に仕掛けたケースです。皆さん、派手な失敗例として憶えているでしょう。そんな失敗例は数多くあるし、さらに記憶にすら残らなかった失敗例はそれこそ山のようにあります。相対的に見ると、独創性がコモディティ化してきた。世の中には独創的な人が溢れかえっていることに皆が気づきはじめたんです。そして、独創性よりも、その独創性を広める力の方が足りない、ということに最近ようやく気づいてきた。つまり「独創性疲れ」というのは広める力が足りなくなってきたともいえる。
―― 世の中はもっともっと広める力を求めているわけですよね。欲望は尽きないといいますか。
江渡 尽きないですね。かつてアルビン・トフラーが「プロシューマ」という言葉を考え出した。プロデューサーとコンシューマの間にプロシューマという層が生まれるだろう、と。従来、プロデューサーはモノやサービスをつくり出す。消費者はそれを買う。その関係の間に入る層がプロシューマです。トフラーの指摘通りに今、進展しています。動画をつくって投稿する人が現れ、それがレベルアップしてYouTuberやTikTokerと呼ばれるようになった。プロデューサーとコンシューマの境い目が薄まっている。
その中の、さらに細かいレイヤーで同じことが起こっています。ひとりの人間がYouTubeで歌手デビューをする、というモデルだけではない。その歌手をデビューさせる仕組みそのものも進化していく。動画づくりや衣装づくり、ステージやチラシの構成など世界全体が進化する。ひとりがピックアップされて伸びるのではなく、進展するにあたってまわりの力を含めて、すべてが進化、進展していく方向に変わった。それが今、起こっていることです。
―― ひとつの優れたタレント、独創力を持っている人がいたら、そこにまた違うタレントをどんどんぶつけていって、そして爆発させる。それが共創という仕組みなんでしょうか。既存の会社のように入社試験だ、面接だとやってる時間がもう惜しい?
江渡 どうなんでしょう。僕が「共創」という言葉を使いだしたのは、5、6年前になります。その時はユーザー参加の枠組みがこれからも続くだろうといわれていました。YouTuberという言葉もなくて「これからYouTubeでそういったものが伸びるかもしれないよね」といわれていたような時代ですよね。その時の考え方はシンプルです。プラットフォームを用意する人がいて、その土台に乗ってひとりで動画をつくって金持ちになる人が出てくる。そういう世界に変わる、と皆が思っていました。
実際にそんな世界になってみると、次はどうなるのか、と皆は考えはじめた。「ひとりが何億円も儲けて、残りの人はゼロ」というモデルではなく、数人〜数十人のチームで、たとえば動画をつくって何千万円を儲ける、というほうがよほど自然ですよね。それが、ここ最近の大きな変化かなと思っています。
協業と共創

江渡 ここから先は「共創とは何だろう」という話になります。今、お話しした時代の変化に共創がどう絡んでくるのか。協業と共創はどう違うのか。協業とはコラボレーション、共創はコ・クリエーションですよね。コラボレーションは昔から行われてきた活動です。ある会社が製品を売るにあたって別の会社とコラボレーションする。ひとつの会社がつくった製品を、違う会社が引き取って商品として売り、お客さんに届ける。こうしたことはずっと行われてきました。
この活動は共創といえるのか。僕は共創とはいえないと思っています。なぜかというと、どのような利益を得るのか、という具体的な見積もりが常にあり、利益を分配する方法をあらかじめ決めてから行っている。定められたヒエラルキーのなかに、決められた役割に沿うことを求められるからです。
一方、共創、コ・クリエーションは達成したい目標があり、その達成のためにお互いが力を尽くす。目標達成のための単一のアプローチを求めません。いい換えれば、参加する各プレイヤーがてんでバラバラに、自分たちの思ったことを実行する。そして、お互いのやっていることが、うまく組み合うときがある。その瞬間が共創だと考えています。共創は状況によって、どんどん変化していくのです。
もうひとつ大事なことがあります。ダイバーシティと利益の関係を説明したグラフがあります。これが面白い。チームがある特定の職種だけが構成されているチームと、さまざまな種類の職種が含まれ、ダイバーシティが高いチームを比較したときに、どのくらいの利益が上がるのか。それを調べた経済学者がいます。特許から生まれる利益を算出すると、平均値は前者のほうが上になります。特定の職種だけで構成されたチームですね。科学者やエンジニアといった専門家です。ダイバーシティが高いチームは平均的な利益率が低い。しかし、ずば抜けた成功に絞ってみると、ダイバーシティが高いチームにしか現れない、という研究結果になった。圧倒的な成功はダイバーシティを実現したチームから生まれていた。
―― 私自身、起業して自分のビジネスを行っていますが、共創を考えると、非常に茨の道のように感じています。
江渡 その通りです。僕は共創を推進する側にいます。「共創を取り入れたけれど、失敗したじゃないか」といわれても困るところがあります。共創すれば成功するわけではない。確率としては低いですよ、ということは予めいっています。そこは誤解を生む可能性はある。
よく例に出すのが、映画『七人の侍』(1954年公開、監督:黒澤 明)です。7人の侍が集まり、チームをつくって村を盗賊から守る。当然、どんどん人は死んでいき、ある人はそんなに役に立たないことがわかったりと、様々なことが発生します。だけど、その能力の違いが最終的な勝利につながる。それが大事です。「村を守る」という目的が極めてシンプルで一致していて、何をすればそれに繋がるのか。それを各自が考えて動いた。結果的にそうした動きが一致したことによって劇的な勝利が生まれた。逆にいうと、そのように頑張ったけど、助からなかったケースも当然あるでしょう。『七人の侍』は物語だから助かったし、勝利もした。
―― 実際の戦国時代では盗賊の方が勝つことが多かったのかもしれません。とはいえ、次の時代を切り開き、閉塞的な社会を打ち破るには「共創」「コ・クリエーション」がカギになると江渡先生は考えていらっしゃるということですね。
江渡 当然、そうです。難しいことなんです。協業と共創がどう違うのか、という話を先ほどしました。外から見てもわからないケースが多いんですよ。中に入ってみると「協業に見えて、これは共創をしていたんじゃないか」「この人たちは共創していたんだ」というように分析してわかることもあります。もうちょっといえば、圧倒的な力の差のもとに共創が成立するケースもある。
たとえば、Appleは社外にいる個人の開発者と共創してソフトウェアを育てることがある。具体的には、SQLite(エスキューライト)というデータベースソフトウェアを開発した人がいる。Appleは、Mac OS Xの基盤技術のひとつとして、そのSQLiteを取り入れることにしました。普通だったら、その開発者を社員として雇えばいい。しかし、そうはしない。あくまでも1対1のパートナーとして取り引きをして、その個人がつくったソフトウェアを尊重する。Appleはその人にお金ではない形で恩返しをしている。企業と個人の間で僕が考える共創が起きています。あっちこっちの場所で共創は生まれているんだろう、とは思います。
―― お話を伺って、私は20年以上前に月刊誌の編集者になったときのことを思い出しました。最初の仕事は映像に関するムック本の編集でした。編集長と副編集長と私しかいない。編集長は何を思ったか、180ページの雑誌の台割を3分割にして「ひとり60ページを好きにつくろう」といったんですね。それなりに大手の出版社です。「編集長と副編集長は好きにやる」「おまえも好きにやれ」といい残して、ふたりとも編集部に帰ってこない。映像に関したページをつくればOKという指示をもとに、20歳そこそこの私はとにかく編集作業をしました。それがすごく楽しかった。自由にやっていいわけですからね。デザイナーを勝手に選んでもいいし、カメラマンも勝手にお願いしていい、自分で絵を描いて掲載してもいい。しかも、自由に創ると編集長と副編集長が喜んでくれる。今、振り返るとあの編集部は協業というより共創だったのかもしれません。「映像」というひとつの目的を達成すればいい、その手段は自由。条件は「俺たち(編集長、副編集長)にかまうな」「俺たちは好きなことやってるから邪魔するな」という感じでしたね。
江渡 いいですね(笑)。20歳だと大学生くらいの年ですよね。僕が大学で教えている年代です。彼らによくいうのは「チャンスというのはピンチの顔をして現れる」。大抵の場合、チャンスというのはそういう形でしか現れないんですよね。あとで振り返ると、あれはチャンスだった、と気が付く。
―― そう思うと、協業は最初からチャンスのような顔をしています。共創は常にピンチですよね(笑)。わけのわからない人が次から次へと現れて独創をぶつけてくる。それに対して、自分も独創で返さなければいけない。常に鍔迫り合い、真剣勝負です。
江渡 その通りです。
自分の「普通の」未来を考える
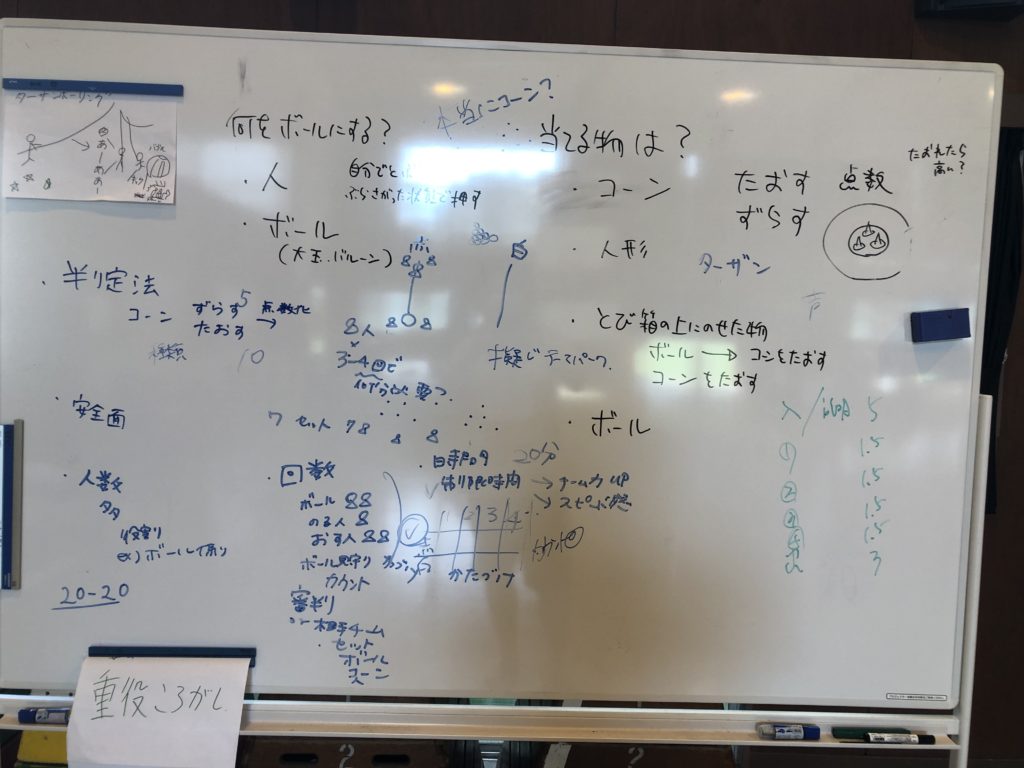
江渡 「スポーツ共創」を人はどうやって知り、参加するに至ったのか。多くはSNSの繋がりで来たというケースです。Facebookのタイムラインで流れてきたり、運楽家の犬飼さんの紹介で知ったとかね。現在のスポーツ共創のフェイズはアーリーアダプターが集まっている状態です。製品化フェイズでいうとキャズム越えをまだしてない。キャズムを越えるにはどうしたらいいのか。そこには一定の戦略性が求められていて、まだ実現できていないというもどかしさはあります。
―― 江渡先生と犬飼さんが「スポーツ共創」という言葉を提唱されました。スポーツ共創を、江渡先生はどのように考えていらっしゃいますか?
江渡 「ニコニコ学会β」という団体を僕が代表しています。その中で下部組織として部をつくることを認めたんですね。その下部組織のひとつに運動会部というのを犬飼さんが立ち上げました。そのきっかけが山口情報芸術センター「YCAM」10周年記念で犬飼さんが制作した「スポーツタイムマシン」です。YCAM10周年記念には僕は審査員として参加しました。このスポーツタイムマシンがとても面白くて、これはいい、展開しようと犬飼さんに申し出たんです。ただ、スポーツタイムマシンそのものは機材が多く、設置作業が大変です。そこで犬飼さんが「スポーツタイムマシンの面白さの革新はそこではない」と主張した。確かにそうだよね、と僕も同調しました。
それなら、どのように展開すべきかを考えるための場をつくろう。ということで、犬飼さんが主導して「ニコニコ学会β 運動会部」を立ち上げました。みなで運動会を研究しよう、というわけです。そのときに僕が考えたのが、「未来の普通の運動会」というタイトルです。
―― 「普通の」とあるのは、日常的に未来で行われているということを示唆している、ということですか。
江渡 そう、「普通の」と付けたのは、たとえば普通の小学校とか中学校の運動会が、30年後、50年後にどうなっているのかを考えたかったからなんです。「普通の」は当時のIT系のトレンドだった言葉です。なぜかというと「未来の」と付けてしまうと、未来っぽい何かになっちゃうんですよね(笑)。未来の「普通の」と限定すると、未来ではそれが当たり前になっていて、むしろそれが当たり前であることを疑っていない何かということになる。それはむしろ、未来感がないものであることが多い。未来になって当たり前になっているものを、今の常識から考えるにはどうすればいいのか。それを考えるのがちょっとトレンドになっていた。そこで「未来の普通の運動会」をやろうと提案しました。
一方で「未来のスポーツ」というのも、ややトレンドになっていた。「未来ではこういうスポーツがあるでしょう」みたいなことを、IT系の研究会で提案されたりする。でも、それはおしなべて実用性に乏しい。「未来のスポーツで使う道具をつくりました」といっても、それで実際にスポーツをして遊んでみたわけではない。未来のスポーツというキーワードを自分たちで定義して、こうなったら面白いよねというのに留まっていた。それって、なんかちょっと違うよね、と思っていました。「未来の普通の運動会」ではどんな風に遊んでいるんだろうか、それを一度真剣に考えたい。
そこから「未来の普通の運動会」のキーワードが生まれ、はじまったのが「未来の運動会」プロジェクトです。いつの間にか、犬飼さんが「普通の」を取っちゃって、「未来の運動会」になりました。
―― 確かに「未来」と聞くと、透明なパイプの中を移動とか、UFOみたいなフューチャーレトロなイメージが思いつきます。しかし、私たちが使っているスマホにしろ、電車のホームから乗客が落ちないようにホーム側に扉が設置されるのも未来です。
江渡 そう思ったわけです。ただ、難しい、と思うことがあります。「スポーツをつくる」「運動会の競技をつくろう」と放り出すと、突飛なものをつくればいい、と思われることが多い。それは面白いこともあるんだけど、その前に「未来の普通の運動会」を真面目に考えてみたい。今はまだ存在していない競技だけど、未来においては当たり前に行われている競技はなんだろうか。そんなことを考えてみたかったんですね。
―― つまり、スポーツ共創のなかで、一緒にスポーツをつくる人間ひとりひとりの中にどんな未来を描いているか、ということですよね。どんな未来にしたいか、という。未来を考えるきっかけになるわけですね。自分が将来、子供が出来たら子供と一緒に遊びたいのか、おじいちゃんおばあちゃんとどうしたいのか。自分も年を取るわけですからね。その時、どう運動会に参加できるかとか、自分事として考えることができる。
江渡 そう、自分事なんです。現在までの経緯をまず説明させてください。「スポーツ共創」には犬飼さんが主導する運動会協会とは別に「超人スポーツ協会」という団体がいます。その2つが合同でスポーツ庁に新規事業として応募するに至りました。その時に、統一した掛け声として「スポーツ共創」というキーワードを決めて、「スポーツ共創会議」という名前にして応募しました。お互い仲は良くて、協力しあっている関係です。この両者が予算を取りに行くのは自然の流れです。
みずほ情報総研をトップにして、「運動会協会」と「超人スポーツ協会」でコラボレーションをして、予算を獲得し、チームを組んで、スポーツ庁の事業「スポーツ共創会議」を進めてきました。「スポーツ共創」というキャッチフレーズにしたのはすごくよかったと思っています。活動の幅が広がりました。東京オリンピックの影響もあるなかで、ちょうどよく「スポーツ共創」の枠組みもつくれることができました。
―― その枠組の中で、保健・体育の先生たちにも「スポーツ共創」は広がっていますね。先生方が教えている小学生や中学生、高校生が20~30年後には社会人として働き、先生になっている人もいるでしょう。今の子どもたちはどんな未来の体育をつくっていくのか。「共創」とは、自分の未来を他人任せにしないということなんでしょうか。
江渡 その理解で合っている気がしますね。自分の未来を他人任せにしない……。非常にその解釈は近い。さっきの話に出てきたキーワードが「未来の普通」ですよね。「未来の普通」は普通の人がつくるんです。それが実をいうと、一番難しいところです。
アーリーアダプターの話もしましたけど、イノベーターがつくり出した何かをアーリーアダプターが捕まえて使いはじめる。しかし、キャズムを超えずに死んでいった事例は山ほどある。普通の人が使う、ということを踏まえていないとそうなる。アーリーアダプターは新しければいい。それは「新しい」という喜びからなんです。でも、普通の人の理解はそこにはない。自分が感じている何か、こういうもの、こういうことをしたい、こういう悩みを抱えてる。そういったことを解決してくれるものを求めている。そこの仕組みって全然違いますよね。その2つがうまく噛み合った時に「未来の普通」が誕生する。
ということは、「未来の普通」を生み出すためにはアーリーアダプターなり、イノベーターに「普通」を理解してもらわなくてはいけないんですよ。これが思ったより、ずっと難しい。当たり前だったり、常識と思っていたものは疑ってほしいのです。
印象に残っている新種目「エア綱引き」
―― 最後の質問です。「スポーツ共創」の枠組みのなかで多くの新種目がつくられてきました。江渡先生がお好きな新種目はありますか?
江渡 パっと出てくる事例でいうと「エア綱引き」です。すごくシンプルで、参加者のひとりが綱引きをする振りをする、というルールです。4対4で綱を引く。だけど、そのうちひとりは引いていない。綱引きに勝った人は誰が引いていないかを当てる権利を得る。当たると「エア綱引き」の勝ち。当てられなかったら、その人は抜ける。ごくごく普通の道具の使い方を変えるだけで、まったく新しい競技になっている。綱引きを競っているように見えて、演技力を競っているのです。
―― 既存のスポーツから、ちょっと軸をずらしているのが面白いですね。
江渡 仰る通り、軸です。あまりにもよくできているから、「未来の運動会」をやるたびにしばしば事例紹介を兼ねて行っています。

いますぐスポーツ共創をやってみよう!

柿崎俊道
編集者。「スポつくWEB」のディレクションを行う。雑誌、書籍の編集者を経て、現在はWEBディレクターなどを行う。
専門分野はアニメ聖地巡礼。聖地巡礼プロデューサーとして、地域のサブカルイベントをプロデュース。埼玉県のアニメイベント「アニ玉祭」、東京都千代田区「アニメ聖地巡礼“本”即売会」、同区「ご当地コスプレ写真展」などを手掛ける。
この記事はスポーツ庁 2019 年度
「スポーツ人口拡大に向けた官民連携プロジェクト・新たなアプローチ展開」にて作成された記事です。
WEBサイトspotsuku.comの終了にともない文部科学省ウェブサイト利用規約に則りコンテンツ加工掲載しております。
出典:スポーツ庁WEBサイトspotsuku.com







